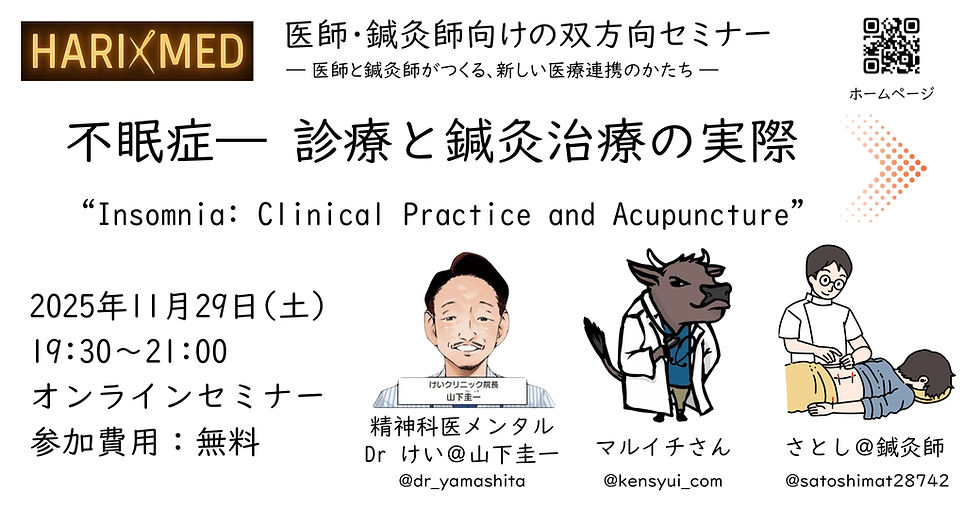- 大慈松浦鍼灸院

- 2025年12月17日
summary:「顔の見える関係」は、少なくとも3要素(顔が分かる/人となりが分かる/信頼して働ける)を含みます。それは、地域連携の構成要素の1つであり、連携を円滑にする機能を持ちます。促進要素は「話す機会」を継続的に構築することです。顔の見える関係とは?
地域連携の文脈で頻用される「顔の見える関係」という言葉を耳にする機会が少なくありません。

しかし、
「顔の見える関係」とは具体的に何を指すのか
それはなぜ連携を円滑にするのか
こうした問いに、学術的に整理された説明は、実はこれまでほとんどありませんでした。
今回ご紹介する論文「地域緩和ケアにおける『顔の見える関係』とは何か?」(Palliative Care Research 2012; 7(1): 323–333)は、この曖昧に使われてきた言葉を、初めて体系的に概念化した重要な研究です。
なぜ「顔の見える関係」が問題になったのか
この論文の出発点は、非常にシンプルです。
「重要だと言われ続けてきた『顔の見える関係』が、何を意味し、どのように地域連携に影響するのかは、これまでほとんど検討されていない」
この研究はどのように行われたのか
本研究は、量的研究+質的研究を組み合わせた探索的研究です。
① 質問紙調査(207名)
地域の医療・介護・福祉従事者を対象に、「地域連携が良好である状態」を構成する項目を評価。
その中に、
「地域でがん患者に関わっている人たちの顔の見える関係がある」という項目が含まれていました。
② インタビュー調査(5名)
実際に地域連携を経験してきた多職種に対し、
「顔の見える関係とは何か」
「それは連携にどう影響するか」
を半構造化面接で深く掘り下げています。
「顔の見える関係」は3つのレベルで成り立っている
この論文の最も重要な知見は、「顔の見える関係」は単一の状態ではないという点です。
① 顔が分かる関係
名前と顔が一致する
顔を思い浮かべることができる
これは連携の「入口」ではありますが、それだけでは不十分であると示されています。
② 顔の向こう側が見える関係
考え方・価値観
仕事のスタンス
話しやすさ、頼みやすさ
得意なこと・苦手なこと
つまり、「どう関わればよいかが分かる関係」です。
③ 信頼できる関係
相手の対応が予測できる
「この人なら返してくれる」という期待がある
責任を前提に一緒に仕事ができる
ここまで到達して、初めて真の意味での多職種協働が成立します。
顔の見える関係がもたらす6つの効果
インタビュー調査から、以下の影響が整理されています。
連絡しやすくなる
誰に言えば解決するか、役割が分かる
相手に合わせて自分の対応を変えるようになる
仕事の効率が良くなる
親近感を覚える
責任を感じるようになる
特に注目すべきは、「顔が見えると、無責任な対応がしにくくなる」という点です。
これは関係性が、行動の質そのものを変えることを示しています。
「顔の見える関係」はどうすれば育つのか
ここで個人的に興味深いと感じた点は、本論文が「顔の見える関係」を精神論としてではなく、
・どのようにして形成されるのか(話す機会)
・その結果、何が起こるのか(連携の変化)
というプロセスに分解して示している点です。
すなわち、
話す機会がある(グループワーク、日常会話、患者を一緒に診る)
→ 性格や強み・弱み、考え方、理念が分かる
→ 連絡しやすくなる、役割が分かる、対応を調整できる、効率が上がる、親近感や責任が生まれる
→ 連携が円滑になる
という構造が明確に示されています。
またこれは、大規模な会議や特別な取り組みではなく、小規模で継続的な対話や、実際の患者対応を通じた協働といった、日常業務の延長線上にある経験こそが「顔の見える関係」を育てることを示唆しています。
その意味で本論文は、忙しい臨床現場においても実践可能な視点を提示している重要な研究であると感じました。
Keyword:顔の見える関係 地域連携 多職種連携 信頼関係 医鍼連携